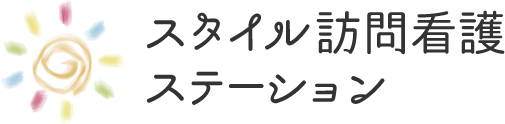生きがいをもう一度取り戻してもらために、訪問という世界を選びました。
リハビリを志したきっかけは、生きがいを失ったじいちゃん
- Q作業療法士を志した経緯は?
- A
農家をやってる鹿児島のじいちゃんが、交通事故で入院することになったんです。野菜や米を子どもたちに送るのが生きがいだったのですが、退院時に先生から「その体だとしんどいから、農業をいっさいしてはいけません」と言われて、生きがいを失ってから体調がどんどん悪くなり、亡くなったんです。
その話を当時高校生のときに聞いて、「もっとやりようがあったんじゃないか?」という思いが出てきたんです。
生きがいって人間にとって大事なことなので、病気や障がいがあっても、生きがいを持ちながら人生を送ってもらいたい。そういうじいちゃんへの思いがあって、それを解決する仕事のひとつがリハビリの職種(作業療法士)かなと思いました。
- Q高校生でそういう考えができるって凄いですよね。
- A
勉強が好きじゃないから早く就職したいと思って工業高校を選びました。ところが、じいちゃんのことがあって「これは違うぞ」と思って、大阪の専門学校の作業療法学科に進みました。
その後、東大阪の総合病院へ進みました。ほとんどが急性期の治療が終わって、回復期(療養型)の患者さんです。当時、作業療法士がゼロ、理学療法士、言語療法士が数人しかいなかったんです。
僕が行くとなったら、作業療法の部門の立ち上げになりなかなか経験できることではないから、行ってみようと思って選びました。
退院したら生活はどうしはるんやろ?というのが気になって

- Q訪問リハビリの世界に来た理由は?
- A
子どもが生まれて、家から近い職場を第一に考えていました。東大阪の病院は少し遠くて。
ずっと在宅でのリハビリに興味は持ち続けていて、病院では患者さんの自宅での生活をイメージしたり、家族の方から情報をもらったりしながら治療を行っていました。
でも、この先(帰宅してから)どうなっていくんやろ?生活はどうしはるんやろ?というのが気になっていて。もともと生活する場でのリハビリの大事さをすごく感じていました。
- Q転職の際に、近くの他の病院は探さなかったんですか?
- A
次に行くとしたら病院以外と決めていました。次のステップとして訪問リハビリの場に身を置きたいと思いました。
訪問リハビリはいっぱい探しましたね。この辺りで当時、訪問リハビリが見つからなかったのと、スタイルのHPを見てすごくアットホームな印象を受けて、そういう職場で働きたいなと思いました。
- Q訪問リハビリは、作業療法士のキャリアとしてはどう思いますか?
- A
それは人それぞれですね。僕としてはもともとの作業療法士を選んだ理由が、「生きがい」というところがありました。
だから、在宅での生きがいをもう一度取り戻すことができたらという思いがあったので、そこは病院よりも在宅のほうが環境が合っています。地域の環境資源もたくさんあるし、生きがいとつながりやすいんかな。
作業療法という以前に、人としての器やサービス業としての在り方は絶対に必要

- Qスタイルを知ったきっかけは?
- A
ネットで探しました。デイサービスもいくつか見ましたが、やっぱり自宅に踏み込まないと分からないことがたくさんあるんですよね。
その人の生活はもちろん、家族さんとの関係もそうですし、実際にトイレまでどうやって行ってるの?ご飯どうやって食べてるの?お家まで踏み込まないと分からないことやったり、その人の大切にしているのもに直接触れることができます。
- Q実際に訪問リハビリを行ってギャップはありましたか?
- A
たくさんありました。病院だと主治医も看護師もいるから、ちょっとおかしいなと感じたらとりあえず呼ぶ、相談できる環境です。
在宅だったら、過去1週間のスケジュールでどういうサービスを受けたのか確認したり、緊急と分かっていたらすぐに呼べるんですが、判断つなかい場合、様子見で行こうかどうかの判断は僕らの責任になってきます。医療者として訪問している責任を強く感じますね。
- Q他に感じたことはありますか?
- A
他には、お家それぞれに文化があるわけですよ。お家の上がり方だったり、避けたほうがいい話題であったり、靴をきゅっと揃えてあがるとか。それを見る家族さんは、この人細かいなと良い印象を持ってもらえます。
作業療法という以前に、人としての器やサービス業としての在り方は絶対に必要です。いま振り返ると病院時代は、ちょっと横柄だったような気がしますね。病院とはちがい、僕らがお客さんとして訪問するので、そこの礼儀はすごく大事かなと思います。
人生の最後まで関われるのが、ありがたい気持ちになる
- Q訪問リハビリのどのような点がおもしろいですか?
- A
本人と家族さん、お家、地域、お店、地域の環境(お花・行事、お祭り)とか、外に出るきっかけが散らばっているので、ちょっと外出ましょうよと誘います。外に出るのを諦めている方もいらっしゃるんですよね。そこを一緒だったら行けるよね、と。
そんな感じでその人の文化に入ることで、僕自信も楽しんでるし、その人の楽しむポイントや表情を見ているとうれしいです。その人の歴史を聞くだけでもけっこう面白かったりもします。
病院は日数が決められているのですが、訪問だと1年2年と長く関わる人がいます。その中で落ちていく方もいてるし、その人生の最後まで関われるのが、僕自信の人生と照らし合わせて、ありがたい気持ちになりますね。
リハビリの効果としての1年の長いスパンをかけることで、良くなっていくところもあったりして。短期間の病院ではなかなか味わえないところかなと。

- Q訪問リハビリはたいへんそうなイメージがあるんですが。どうですか?
- A
今でも最初は、どんな人かな?という緊張はあります。でも、基本的に皆さん待ってました!という方が多いです。期待されている。始めは様子を伺うイメージがあるけけど、だんだんと打ち解けてくる。それがもっとできることないかな?とモチベーションに繋がったり、もう少しできないかな?と思って。振り返ったら、最初の緊張もそのあとのモチベーションの糧になっています。
リハビリでよくなるところもあれば、良くならないところもあるし、でも病気や障がい、年齢と折り合いをつけながら生活していくわけですが、それらがあっても地域で生活していく手助けになるのが大事なところです。
暴言とは裏腹に・・・
- Q印象的な利用者さんのエピソードは?
- A
たくさんありますね。口の悪いおじいさんがいました。訪問したら「おまえ、ぷーよう、ぷーよう」と言うんです。「ぷーようってなんですか?」と聞いたら、中国語で「不要ってことや」。そういうことですかぁ(笑)と言って、軽く流しながら始めていくんです。
奥さんと2人暮らしで、ぼくが訪問する前から「あいつは来ないのか?来ないのか?」と奥さんに言っていたみたいなんですね。軽く暴言を吐かれるけど、待ってたんかな?ちょっと思ってくだってたんかな?と思いながら訪問していて。
亡くなった後も1年に1回ぐらいお線香しに訪問するのですが、奥さんが「あのとき毎回待ってたんですよ。森さんにはすごくひどい言葉をたくさん言うてましたが、いつも待ってましたよ」と言ってくれます。

- Qたいへんなこともあるけど、冥利に尽きる感じですね
- A
病院のときは亡くなったら終了ですが、訪問でも亡くなったあとでもご家族で合うことで、行かせてもらってよかったなと、こっちが温かい気持ちと感謝の気持ちがあります。
亡くなった後に訪問できるのは全員ではないですが、人生の最後に自分みたいな者が関わることができる、いい経験をさせてもらってるなと思います。
施設にも訪問リハビリに行くのですが、その方も暴言を吐く方で、だんだんと落ちてきて、暴言を吐く力も弱くなっていって・・・。もっと元気出してという思いもあるし、そんなに無理しなくていいよという思いもあるし。だんだん神聖な人に思えてきて、心が洗われてくるような気がしてきますね。それが人の生なのかなと思うんですよ(笑)。
自分も利用者さんも、自分で考え自分で決める力がつく
- Qスタイルの良いところは?
- A
24時間対応ではないですが、利用者さんの生活を支えるためにいろんな支援をしています。とはいっても訪問時間は限られていますよね。
では何が一番大事かと言うと、その人が家で生活していく力を育む、その力がいちばん大事なんですよね。そのために投げかけるわけですよ。今はこういう状況でどうしますか?こういう方法もあるし、こういう方法もあるし、選択肢を提示して決めてもらう。自分で決める感覚が大事なんですよね。自分で決めるのが自分で生き抜く力につながってくるんです。
スタイルの看護って自学自立をすごく促すんです。「じゃあ、どうする?じゃあ、どうする?」とめちゃ言うてます。
電話を頻繁にかけてきて「助けて助けて」という人も、自分の中でどうするかある程度考えて電話するようになってきた。報告だけみたいな。それこそが何かあったときに、自分で生きていく力になります。

- Q普通は助けてほしいと思いますよね
- A
依存体質をつくってしまうと一人で生きていけない、夜寝れないときに寂しくてどうしようもないとか、1人の時間を過ごせなかったら家では生活できないんですよ。だから自分で考え選択する力が必要になってくる。スタイルが一番大事しているところかなと思います。
書面には残せない利用者さんの微妙なニュアンスを、顔を合わせて共有できる
- Q他にスタイルの良いところは?
- A
毎朝朝礼するんですよね、朝礼の前後とかで看護、リハビリ合わせて情報共有できます。書面でなくて直接顔を合わせて、申し送りができる環境はすごくいいです。
介護保険を利用した患者さんだけでなく、精神科の方もするんですね。看護もいっしょなんですけど、作業療法士で精神科の訪問もしつつ体のことも見ますというところは、強みです。精神科の方でも、体の不調があるし、お年寄りの方もいらっしゃるので、リハビリを提供できます。
- Qスタッフ間の雰囲気はどうですか?
- A
近くて話しやすいです。相談しやすい、情報共有しやすいです。直行直帰の職場もありますが、スタッフ間の共有がきちんとできています。書面には残せない微妙なニュアンスだったりとかあるので。
利用者さんは自分の思いを100%伝えてくれるわけじゃなくて、訪問者によって表現しきれないこともあったりします。
例えば、足が痛いという利用者さん。大丈夫そうに感じる場合、次の訪問スタッフにまた見ておいてください、とか書面でできることもありますが、微妙なところがたくさんあるので、直接顔を合わせて情報共有できる場は、すごく大事かなと思います。
訪問から帰ってきて、今日こういうことあってー、とキャッキャと前向きに共有したりしています。書面だけではけっこうディープになりがちなことを、申し送る時にくだけた感じ次の備えができます。
管理者の中村は「木の幹」
- Q管理者の中村浩美さんはどんな存在ですか?
- A
浩美さんが木の幹で、僕らが葉っぱみたいな。人間味もあって、温かいときもあれば、ここきっちりの場面もあります。
あと、文章書くの上手です。ここ最近、朝礼の中で訪問看護の良いところをスタッフ間で話し合うことをやってるんですが、僕なんか何個か箇条書きなんですけど、浩美さん居酒屋のメニュ表のようにあって、この中から選んでください、それを話します、どうぞ!という感じ(笑)。
なにを聞いてもたくさん話してくれるし、浩美さんはトップとして圧倒的に実行してきてるので、すごい存在ですね。

スキルよりカルチャーフィット
助け合いの環境で働きませんか?
自分の弱みと向き合い、補い合える環境を一緒に作っていける人を探しています。